ホーム > 生涯学習 > 神戸市立図書館 > 神戸市立図書館トップページ > 神戸の郷土資料 > KOBEの本棚-神戸ふるさと文庫だより- > バックナンバー(19号~60号)KOBEの本棚 > KOBEの本棚 第23号
KOBEの本棚 第23号
最終更新日:2020年6月3日
ここから本文です。
-神戸ふるさと文庫だより-
- 第23号 平成9年6月20日
- 編集・発行 神戸市立中央図書館
2号館開館によせて
震災から二年四ヶ月をへて、中央図書館旧館の復旧工事が完了し、六月三日、新しく「2号館」として再開した。アーチ型の窓を特徴とするロマネスク様式を踏襲し、以前の雰囲気を残している。玄関左側には旧館の正面壁画上部に掲げられていた「神戸市立図書館」の文字をモニュメントとしている。風格ある書体が、かつての歴史ある建物を偲ぶよすがである。
また、知る人は少ないが、この文字の上部には、かつて、図書館の館章もあった。市章、トーチ、図書、月桂樹を組み合わせた図案で、大正十年十月、大倉山に図書館が開館するに当たり、公募されたデザイン。作者は大阪ヴォーリズ建築事務所所属の林徳洙氏で、前号で紹介のW.M.ヴォーリズとのわずかな接点でもある。
2号館には、あの日を語り継ぐための「震災資料展示室」や韓皙曦氏の収集による、三万点を越す韓国・朝鮮関係資料のコレクション「青丘文庫」など、新しい魅力も加わった。市民はもとより、広く人びとに求められる場所となることを希望している。
 2号館
2号館
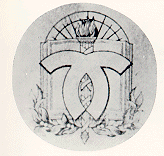 館章
館章
新しく入った本
むかしの神戸-絵はがきに見る明治・大正・昭和初期
和田克巳編著(神戸新聞総合出版センター)
 神戸の街は、ハイカラ、モダン、エキゾチックなどで形容される。その原型を作ったのが居留地の外国人たちである。
神戸の街は、ハイカラ、モダン、エキゾチックなどで形容される。その原型を作ったのが居留地の外国人たちである。
一方、神戸には、古い街として、酒造りで有名な灘の町や北前船などの港としてにぎわった兵庫の町が存在する。神戸は、新旧和洋が混在する不思議な街である。絵葉書を眺めていると神戸の変貌ぶりがよくわかる。そしてまた、大震災に遭遇した神戸は、変わろうとしている。この絵葉書集には、父母や祖父母が生きた時代をただ伝えるのではなく、子孫に神戸の街をどのように残すかを考える助けに、という編者の願いもこめられている。
ひょうごの美術家たち-戦後半世紀の出逢い
伊藤誠(神戸新聞総合出版センター)
美術担当記者から美術館副館長を務めた著者が、新聞や図録に寄せた文章を、画壇の流れに沿って一冊にまとめた。
氏が美術家たちを見る眼は鋭く、かつあたたかい。そして、実際に出会った時のエピソードが語られているために、今は故人となった小磯良平や田村孝之介、また、現在活躍中の中西勝など、新旧兵庫の美術家たちの人となりにふれることができる。
須磨の歴史散歩
田辺眞人(神戸市須磨区役所)
 本書は五十九年刊の『須磨歴史小事典』の改訂版。改訂作業と震災が重なり、刊行が二年遅れたが、古来より近畿の大地震が、鴨長明や須磨寺の古記録にどう記録されてきたかについて述べた、「震災の歴史に学ぶ」が加えられた。版型、活字組みを変え、軽快な装いとなったが、内容の充実度は変わっていない。歴史と文学の地、須磨を知るには最適の書である。
本書は五十九年刊の『須磨歴史小事典』の改訂版。改訂作業と震災が重なり、刊行が二年遅れたが、古来より近畿の大地震が、鴨長明や須磨寺の古記録にどう記録されてきたかについて述べた、「震災の歴史に学ぶ」が加えられた。版型、活字組みを変え、軽快な装いとなったが、内容の充実度は変わっていない。歴史と文学の地、須磨を知るには最適の書である。
イヌワシを追って
山本靖夫(神戸新聞総合出版センター)
 著者は、神戸新聞時代の取材がきっかけで、二十七年間イヌワシの観察を続けている。現在は、日本イヌワシ研究会の理事として活躍。
著者は、神戸新聞時代の取材がきっかけで、二十七年間イヌワシの観察を続けている。現在は、日本イヌワシ研究会の理事として活躍。
イヌワシは、とめどない開発に生存を脅かされ、繁殖率が年々低下し、絶滅の危機にさらされている。
本書では、山での寒さや緊張感に耐えながら観察、撮影したイヌワシの生態が明らかにされている。また、深山を駆けめぐる著者の姿から、喜びや悲しみが伝わってくる。
「美しい日本」に殉じたポルトガル人-評伝モラエス
林啓介(角川書店)
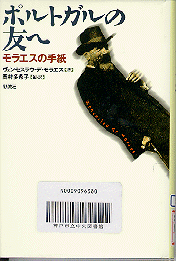 モラエスは初代神戸領事として明治中期の日本へやって来た。領事としての仕事の他に、日本に関する多くの作品を残した文人でもある。海軍の軍人としてアフリカ、マカオと遍歴した後、極東の島国に魅せられ、ついには骨を埋めることになる。
モラエスは初代神戸領事として明治中期の日本へやって来た。領事としての仕事の他に、日本に関する多くの作品を残した文人でもある。海軍の軍人としてアフリカ、マカオと遍歴した後、極東の島国に魅せられ、ついには骨を埋めることになる。
近代化を急ぐ日本でモラエスが愛したものは何か。彼の数奇な生涯と複雑な心情が詳細に記された一冊。また、同時期に出版された『ポルトガルの友へ』岡村多希子編訳(彩流社)は、故国ポルトガルへの複雑な思いを語る膨大な書簡の一部である。
ラスト・ラヴ
玉岡かおる(新潮社)
一九九一年神戸。二十五才のヒロイン、アンナ。旧居留地のファッションビルを中心に、事業を展開する母。血のつながらぬ兄、ダイチとタイガ。幼い頃死んだ、登山家だった父。
アンナとタイガは、兄妹となった日から互いにひかれた。ようやく素直になれた二人を、さまざまな障害が阻む。そんな彼女を静かにつつむダイチ。決意の前に行った父が眠るネパールでの、思いがけないタイガとの再会。しかし、ダイチとの現在をアンナはえらぶ。
そして、あの大震災。派遣医師としてタイガは神戸にはいる。存在の根底をもゆるがす自然の力は、二人を再び結びつける。それは最後の、そして最初からの摂理だったのかもしれない。
明日をよむ 商い文化の時代
中内功・森毅(未来文化社)
中内氏は大正十一年、大阪に生まれ、四歳から神戸で育った。家業は工場街にある薬局で、親の働く姿を見て育った。また、南方戦線から九死に一生を得て生還したのも、その後の生き方に影響を与えたと語る。対談相手の森氏は五歳年下。戦中戦後を生き延びた経験は、中内氏の人物像や、情報産業化を目指す経営者の哲学を切れ味良く引き出している。
魚たちの声が聞こえますか?
中村翔子(PHP出版)
 阪神・淡路大震災では、須磨海浜水族園も大きな被害を受けた。五十八時間続いた停電のため、死んでゆく魚たちを眼前に、なすすべがなかったという。本書は、水族園の開設当初から、震災後の復旧までを追った児童向けノンフィクションである。メジロザメの捕獲やピラニアの飼育など、オープン時の苦労や愛情をこめた飼育の様子が丁寧に描かれているため、楽しさと、同時に震災時の無念さが伝わる。
阪神・淡路大震災では、須磨海浜水族園も大きな被害を受けた。五十八時間続いた停電のため、死んでゆく魚たちを眼前に、なすすべがなかったという。本書は、水族園の開設当初から、震災後の復旧までを追った児童向けノンフィクションである。メジロザメの捕獲やピラニアの飼育など、オープン時の苦労や愛情をこめた飼育の様子が丁寧に描かれているため、楽しさと、同時に震災時の無念さが伝わる。
阪神大震災復興市民まちづくりVol.8
阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局編(学芸出版社)
 震災から二年余がすぎ、神戸は街全体としては、少し落ち着いてきたようにみえる。しかし、被害の大きかった地域のまちづくりは、なかなか進まない。
震災から二年余がすぎ、神戸は街全体としては、少し落ち着いてきたようにみえる。しかし、被害の大きかった地域のまちづくりは、なかなか進まない。
そのような中、各地区のまちづくりニュース紙をまとめ、神戸はもちろん、全国へ被災地の状況を発信しつづけてきた本書が、当初の予定どおり二年を迎えた本号で終刊する。
まちづくり支援ネットワークは、各地区まちづくり協議会などの団体のネットワーク化をはかり、物心両面で支援し、被災地の復旧、復興に尽くしてきた。その活動は、本書が終刊しても続く。
その他
- 勝てるには理由がある。 仰木彬(集英社)
- 神戸都市財政の研究 池田清(学文社)
- KOBE洋菓子物語 村上和子(神戸新聞総合出版センター)
- 南京町虎笛奇譚-風水バスターズ 麻生燦(角川書店)
- 京阪神の市場 商店街(昭文社)
- 返信-母の便りに- 田尻泰雄(新風舎)
- 阪神大震災に見る木造住宅と地震(鹿島出版会)
- 神戸の復興を求めて 神戸大学震災研究会編(神戸新聞総合出版センター)
- 震災時のトイレ対策-あり方とマニュアル-(日本消防設備安全センター)
わが街再発見コーナー新着図書
北図書館
レクリエーション・民俗芸能
- 一行物 上・下 芳賀幸四郎(淡交社)
- いまからはじめる中高年の山歩き 川村匡由ほか(ミネルヴァ書房)
- 京阪神からのファミリーフィッシング 藤岡ひとし(山と渓谷社)
- 自分流山登り虎の巻 羽根田治(雄鶏社)
- 初歩からはじめる木彫 渡辺一生他(日本放送出版協会)
- 煎茶の世界 煎茶文化研究会編(雄山閣出版)
- 楽しいキャンピング 関忠志(誠文堂新光社)
- 茶道具の手入れ 東京美術青年会編(淡交社)
- 定年後は山歩きを愉しみなさい 小倉厚(明日香出版社)
- 能百十番 増田正造(平凡社)
- フラワーアレンジメント 瀬戸信昭編(日本ヴォーグ社)
ランダム・ウォークイン・コウベ
旗振山
須磨浦山上遊園の北側、摂津播磨の国境に、標高二五二・八メートルの旗振山があります。頂上に立つと、西には明石方面と明石海峡大橋、淡路島を、東にはポートアイランド、六甲アイランド、遠くには大阪の市街を見ることができます。このような眺望を持つ旗振山は、「旗振り通信」がおこなわれた場所と伝えれられています。
明治三十一年の「風俗画報」には、大津追分の山上で、望遠鏡をのぞきながら懸命に白旗を振る二人の男が描かれています。彼らは、大阪堂島の米相場を一刻も早く各地に伝えようと旗振り通信をしているところです。当時、同様のことが各地でおこなわれていました。
江戸時代から諸藩の蔵米が取り引きされてきた大阪堂島の米市場は「諸国第一の取引所」であり、そこで立てられる米相場は全国の米価の目安となります。投機的な米の先物買いもさかんで、商売の命運を左右するその日その日の相場を、各地の商人たちはできるだけ早く知る必要がありました。
堂島で振られた旗の信号は、神戸、京都、津、和歌山、広島など各地へ、リレー式で伝えられました。堂島から神戸へは、武庫川堤─芦屋旗振場─神戸諏訪山─兵庫米会所へと伝えられ、そこから再び、高取山─旗振山─明石和坂─姫路・岡山方面へと送られました
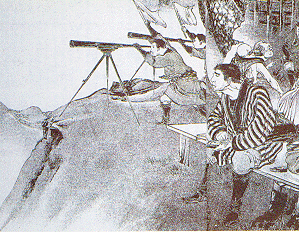 旗振り通信の中継所は、三里から七里の間隔で、山上のほか、市街地の屋根の上に櫓を建てて設けられました。快晴で望遠鏡の見通しがよい日は畳半分ほどの小旗を、曇天には畳一枚ほどの大旗を振ります。旗の信号は、いろは四十八文字と数字で、値段や場所などを示しており、途中で盗み読まれないように、日によって信号の意味を変えることもあったそうです。
旗振り通信の中継所は、三里から七里の間隔で、山上のほか、市街地の屋根の上に櫓を建てて設けられました。快晴で望遠鏡の見通しがよい日は畳半分ほどの小旗を、曇天には畳一枚ほどの大旗を振ります。旗の信号は、いろは四十八文字と数字で、値段や場所などを示しており、途中で盗み読まれないように、日によって信号の意味を変えることもあったそうです。
ところで、明治二十六年(一八九三)には神戸と大阪で電話交換業務が開始されています。にもかかわらず、なぜ旗振り通信が大正初期まで続けられたのでしょう。
米一升が十二銭だった当時、市内一回五銭、市外十五銭、加入料三十五円の電話料金はかなり高いものでした。また「郵便より遅い長距離電話」と揶揄されるほど、市外通話はつながるのに時間がかかりました。旗振り通信での大阪─神戸の所用時間は五~七分、岡山まででも約四十分といいますから、速さの点では電話より信頼のおける通信手段だったのです。
郷土史家の調査により、明治末期から大正初めの一時期、旗振りの中継所は旗振山ではなく、その北東にある栂尾山であったということがわかってきました。多井畑に住んでいた旗振り人が、毎日、弁当を肩にかけ栂尾山に登っていたという話や、子どもの頃、栂尾山で旗振り用の据え付け望遠鏡をのぞかせてもらったという話が、聞き書きの形で残っています。
旗振り通信は、電話の普及にともない消えていきました。市街地の高層建築や煤煙の増加も原因の一つでしょう。今は、その名残を旗振り山の名にとどめるだけになっています。
- KOBEの本棚 第60号
- KOBEの本棚 第59号
- KOBEの本棚 第58号
- KOBEの本棚 第57号
- KOBEの本棚 第56号
- KOBEの本棚 第55号
- KOBEの本棚 第54号
- KOBEの本棚 第53号
- KOBEの本棚 第52号
- KOBEの本棚 第51号
- KOBEの本棚 第50号
- KOBEの本棚 第49号
- KOBEの本棚 第48号
- KOBEの本棚 第47号
- KOBEの本棚 第46号
- KOBEの本棚 第45号
- KOBEの本棚 第44号
- KOBEの本棚 第43号
- KOBEの本棚 第42号
- KOBEの本棚 第41号
- KOBEの本棚 第40号
- KOBEの本棚 第39号
- KOBEの本棚 第38号
- KOBEの本棚 第37号
- KOBEの本棚 第36号
- KOBEの本棚 第35号
- KOBEの本棚 第34号
- KOBEの本棚 第33号
- KOBEの本棚 第32号
- KOBEの本棚 第31号
- KOBEの本棚 第30号
- KOBEの本棚 第29号
- KOBEの本棚 第28号
- KOBEの本棚 第27号
- KOBEの本棚 第26号
- KOBEの本棚 第25号
- KOBEの本棚 第24号
- KOBEの本棚 第23号
- KOBEの本棚 第22号
- KOBEの本棚 第21号
- KOBEの本棚 第20号
- KOBEの本棚 第19号